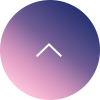- 凍結保存物の保存期間延長の
手続きのご案内 - 凍結胚の「凍結開始日」と
「保存期限日」について - 一年毎に保存期間延長の
手続きが必要です - 凍結精子の「精子凍結日」と
「保存期限日」について - 手続き方法
- 凍結保存延長料金
- 手続きの関係書類はこちらです
- 当院で体外受精をされ、
凍結胚を保存している方へ
凍結保存物の保存期間延長の
手続きのご案内
凍結配偶子・胚の保存期間と
その延長ついて
保存期間は凍結開始日より一年間としております。凍結保存は技術的には長期的に可能です。しかし、1988年4月の日本産科婦人科学会の「ヒト胚および卵の凍結保存と移植に関する見解」により「胚の凍結保存期間は、夫婦の婚姻の継続期間であって且つ卵を採取した母体の生殖年齢を超えないこととする」と定められており、また配偶者死亡後の胚移植は裁判例で禁じられていますので、当院では次の場合には凍結胚は廃棄することになります。
- 夫婦が離婚した場合
- 夫婦またはそのどちらか一方が凍結胚の廃棄を申し出た場合(廃棄申込書が必要)
- 生殖可能年齢を超えたと当院が判断した場合
- 一方の配偶者が死亡した場合
- 不妊治療を中止する場合
- 凍結保存期間を延長しない場合
- 保存延長希望はありながら、延長期間分の凍結保存料の支払がなく、何らかの理由により連絡が取れない場合
凍結胚の「凍結開始日」と
「保存期限日」について
凍結胚の「保存期限日」は採卵周期ごとに設定されます。もし同一の採卵周期に複数の凍結胚がある場合、その周期内で最初に胚を凍結した日を「凍結開始日」とし、「凍結開始日」から半年後の前日を、その周期内で凍結したすべての胚の初回の「保存期限日」と定めます。
初回の延長手続きがなされた場合、次回の「保存期限日」は「凍結開始日」から一年後の前日となります。
異なる採卵周期の凍結胚の
取り扱い
異なる採卵周期で複数の凍結胚がある場合、それぞれの「保存期限日」に応じて保存期間延長の手続きが必要です。そのため、申請書にはそれぞれの「採卵日」の記入が必須です。
一年毎に保存期間延長の
手続きが必要です
当院で、胚・精子を凍結保存されている方は、「一年毎」に「自らの申し出」による保存期間延長の手続きが必要です。保存期限日の2ヶ月前から保存期限日までに、凍結保存延長料金の支払いがない場合や申請書(「未申請時の凍結物(胚・精子)廃棄同意書 兼 凍結胚・凍結保存期間の延長申請書」)の提出がない場合は、凍結物の保存が終了となります。
申請書の提出の際は、ご夫婦双方の署名が必要です。予めご確認の上、保存期限内の手続きをお願いいたします。尚、申請書には「採卵日」、または「精子凍結日」の記入が必須です。
凍結精子の「精子凍結日」と
「保存期限日」について
精子を凍結した日を「精子凍結日」とし、「精子凍結日」から一年後の前日を初回の「保存期限日」と定めます。
初回の延長手続がなされた場合、次回の「保存期限日」は「精子凍結日」から一年後の前日となります。
「精子凍結日」が異なる
凍結精子の取り扱い
「精子凍結日」が異なる凍結精子がある場合、それぞれの「保存期限日」に応じて保存期間延長の手続きが必要です。そのため、申請書にはそれぞれの「精子凍結日」の記入が必須です。
手続き方法
延長申請手続きの方法は、「郵送(現金書留)による手続き」または「ご来院での手続き』のいずれかの方法となります。
①郵送(現金書留)による
手続きの流れ
下記の三点を現金書留封筒へ入れ、なかむらアートクリニック宛に郵送してください。
- 署名した申請書(「未申請時の凍結物(胚・精子)廃棄同意書 兼 凍結物保存期間の延長申請書」)
- 凍結保存延長料金
- 宛先を記入した返信用の封筒
現金書留の郵送先
〒222−0033
横浜市港北区新横浜2−5−14 WISE NEXT 新横浜 9F
なかむらアートクリニック 凍結延長手続き係
②ご来院での手続きの流れ
ご来院される前日までに、受付に電話連絡をください。
当日は下記の三点をご持参ください。尚、当院の休診日、診療時間外の手続きはお受けできません。
- 署名した申請書(「未申請時の凍結物(胚・精子)廃棄同意書 兼 凍結物保存期間の延長申請書」)
- 凍結保存延長料金(受付でのお支払い方法は現金のみです)
- 宛先を記入した返信用の封筒
凍結保存延長料金
| 種類 | 料金 (税込/一年間) |
|---|---|
| 凍結胚 | 44,000円 |
| 凍結精子 | 22,000円 |
*今後、凍結保存延長料金が変更になる場合もございます。ご了承ください。
手続きの関係書類は
こちらです
Adobe Readerをお持ちでない方はこちらからダウンロードしてください(無償)
当院で体外受精をされ、
凍結胚を保存している方へ
治療再開時期について
産後一年は子宮を休めせる期間です。出産後11ヶ月以上が経過しましたら再診予約から予約をおとりください。出産後の月経が2-3回あり、授乳が終了していることも必要です。
治療を終了する方
廃棄同意書が必要です。廃棄同意書は凍結保存延長書類とは異なります。廃棄同意書をホームページより印刷し署名後送付してください。必ず凍結期限内にお願いいたします。
保険診療での凍結胚更新について
保険診療での凍結胚更新の対象
以下の条件を全て満たしている方のみ、保険で更新が可能となります。
- 移植に向けて継続的に通院中の方。(感染症採血、超音波検査、医師の診療が済んでいる方)
- 治療計画を作成した方(ご夫婦の来院が必要です)
- 移植周期の治療開始年齢が43歳未満の方
なお、妊娠や出産後等や自己都合で不妊治療に係る治療が中断されている場合であって、患者さまの希望により、凍結保存を継続する場合には自費での(44,000円(税込/ 1年間)となります。